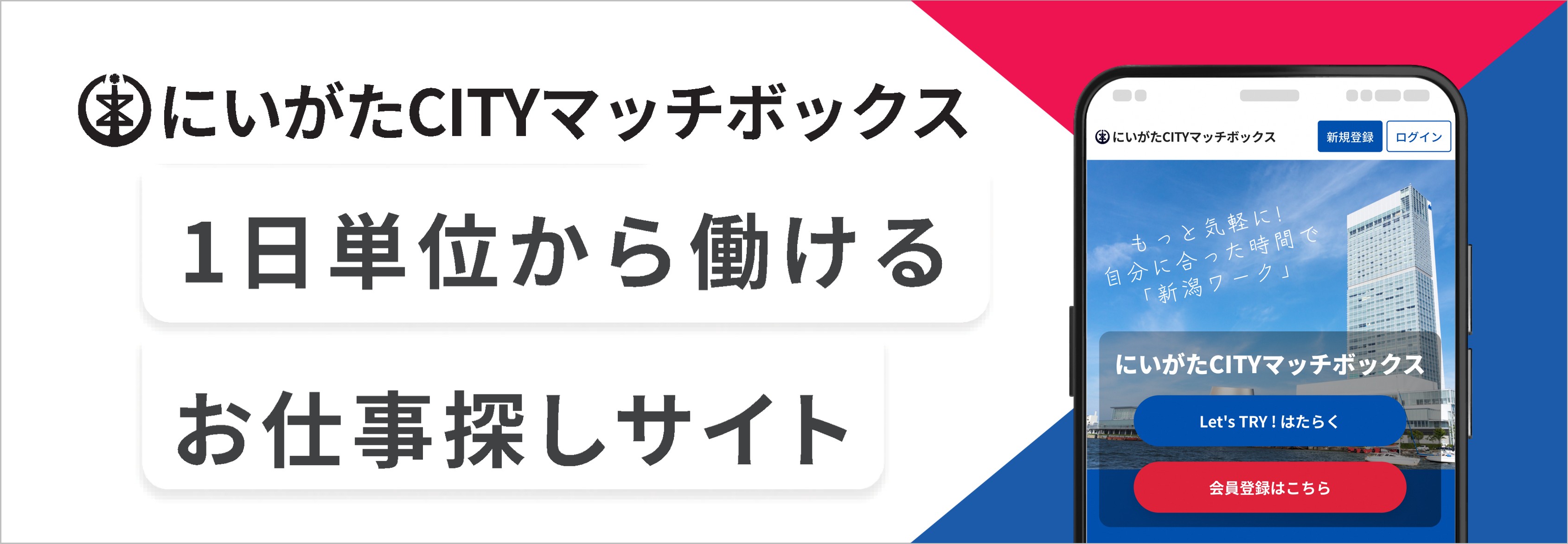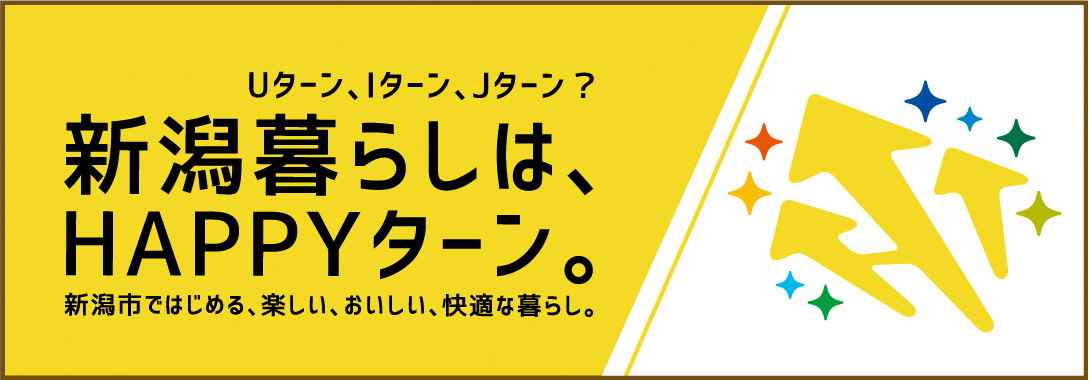interview インタビュー
【令和6年度 働きやすい職場づくり推進企業表彰 新潟商工会議所特別表彰を受賞】「取り組み」を「仕組み」に。事情も価値観も異なる人が、安心してその人らしく働ける多様な働き方を

新潟市中央区に本社を構える株式会社村尾技建。若者の採用・育成に積極的な取り組みを行い、「ユースエール認定企業」、6年連続「健康経営優良法人(中小規模法人部門)」などの認定を受け、「令和6年度新潟市働きやすい職場づくり推進賞」、「新潟県経営者協会特別表彰」にも選出されました。その取り組みの経緯や工夫について、代表取締役社長の村尾 治祐(むらお・はるまさ)さん(以下、村尾社長)、管理部 課長代理 齋藤 百代(さいとう・ももよ)さん(以下、齋藤さん)にお話を伺いました。
経営者目線で知った当たり前ではない長時間勤務
働きやすい職場づくりに取り組み始めたきっかけを教えてください。

村尾社長:私が入社した1999年当時、技術部門は「長時間労働が当たり前」という空気でした。閑散期でも毎日2〜3時間の残業、繁忙期は退社時間が23時、納品前は深夜になることも珍しくありませんでした。
車通勤が中心で、仕事後にどこかへ寄る習慣もなく、職場と自宅の往復が日常でした。正直、その状況を特別つらいとは思っていませんでしたし、「こういうものだ」と思っていたのだと思います。転機は2015年前後です。経営側の立場になり、異業種の方々と話す機会が増えると、残業が少ない働き方が『普通』の世界があると知りました。社員の健康面はもちろん、経営の観点でも長時間働くことが必ずしも生産性の向上につながるわけではありません。限られた時間で価値を出すことに切り替えようと考えるきっかけになりました。
事情も価値観も異なる人が、安心してその人らしく
「働きやすい職場」とは、どのような職場だと考えられていますか?
村尾社長:事情も価値観も異なる人が、それぞれ安心してその人らしく働ける。仕事を通じて自分の成長を実感できる。そんな職場を目指しています。建設業は以前“3K”と言われていましたが、今は「給料が高い・休暇が取れる・希望が持てる」という“新3K”、さらに“かっこいい”を加えた“新4K”を業界全体で掲げています。“かっこいい”とは、最新技術を扱うことだけでなく、働き方そのものがスマートで、家族や地域からも応援される状態だと考えています。
現場ではICT施工が進み、遠隔操作や自動化も広がっています。私たちの仕事は状況把握や判断が必要で、人の力が不可欠な領域もまだ多い。それでも技術進化に合わせて役割分担を見直し、誰もが働きやすい魅力ある職場に近づけたいです。
育成の考え方も見直しました。以前は、半年から1年ほど先輩について仕事を学び、あるタイミングで一気に仕事を任され独り立ちする形でした。責任を負うことで速く鍛えられる反面、離職のリスクが高い面もありました。今は責任の持たせ方に段階をつくり、成果と経験が噛み合うペースで若手を育成しています。
土台となる体制づくりによって生み出す変化
働きやすい職場づくりのために取り組まれていることを教えてください。
村尾社長:当社の中でも特に働き方改革の必要性が高いのは、技術部門だと考えています。繁忙期には業務が集中し、災害時には休暇中でも現場に駆けつけて対応することが求められるため、今回はその部門に特化したお話になります。技術者の本業は“考える”ことです。その時間を確保するために、図面作成や写真整理、製本といった作業は技術事務を配置して負担を分散しています。さらに、創業初期から会社を支えてくれているベテランメンバーに活躍してもらうため、若手の指導や業務の管理をお願いしています。各案件にベテラン技術者を担当配置し、若手のOJTと品質確保を両立。単なる指示ではなく、課題にぶつかった時に一緒に考え、なぜその判断が必要かを言語化して伝える。そうした伴走を通じて“考える力”が育ち、手戻りが減ることで労働時間の短縮にもつながっています。
もちろん課題もあります。ベテランの水準が高いがゆえに、若手からは「難しい」「時間内に収まらない」と映ることがある。そこで衝突を恐れず対話し、要求水準の背景や意味をすり合わせる。品質を守りつつ現実に若手が達成できる水準に落とすプロセスそのものが、会社にとって大事だと考えています。
齋藤さん:他にも具体的な取り組みとして、テレワークを推進していて、社員全員テレワークをできる環境が整っています。ただ、その中で個人の意識の軽重により進まない面はあります。慣れた仕事、仕事のやり方を変えることが難しいというところが課題でもあります。
村尾社長:北海道であれ沖縄であれ、普段はどこで仕事をしても良い時代になってきています。そして、場所に縛られない働き方は、BCP(有事の際の事業継続)にも直結します。コロナ禍でテレワークが普及し、当社もそのタイミングで対応しましたが、また大きな災害が起きるかもしれない。我々の仕事では、どうやってその災害復旧復興に関わっていけるのか、その体制作りが大事なところです。
実際に怪我で出社できない社員が在宅で1か月以上業務を継続した例があり、平時からルールとセキュリティ、コミュニケーションの手順を整えておくことの重要性を感じました。
丁寧なコミュニケーションが実現した離職率の低下
取り組みによる成果があれば教えてください。

齋藤さん:新卒の離職率は、ここ三年間ゼロなんです。業務の偏りが少しずつ解消され、定着につながっているのだと思います。定時退社の習慣化や業務の効率化が進み、残業時間の削減にも一定の効果が出ています。
村尾社長:大学卒業後に地質を勉強してきた社員が比較的多いのですが、そういった専門分野の勉強をせずに高校卒業後に入社した社員も離職することなく働き続けています。新人をフォローできているということかなと思っています。
齋藤さん:具体的には、入社半年くらいのタイミングでフォローアップ面談を設け、部署外の目線で変化に気づけるような仕組みを続けています。
村尾社長:それと、当社では経営陣と社員との距離が非常に近く、駆け込み寺のようになっています。副社長は技術畑なので、技術的に何かあると副社長のところに来ますし、私は少しとぼけたように見せながら、表情を伺ったり部署の空気を聞いてみたりして、何か察知すればフォローすることもあります。
例えば、会社で規定が変わることがある。しっかり伝わらない中で制度やルールが動いてしまうと、それが不満で離職につながることもあるわけですよね。だから趣旨やメリットはもちろん、デメリットも含めた全体像をわかってもらうことが大切だと思っているので、ヒアリングを行いながら、誤解のないようになるべく伝えるようにしていますね。
最大の障壁は「当たり前」という思い込み
取り組みの中で、障壁となったことはありますか?
村尾社長:「長く悩むほど偉い」「時間をかけた分だけ頑張った」——そんな、業界に根づいた「当たり前」という思い込みがあります。私たちは頭脳労働でありコンサルタントなので、かける時間がはっきり決まっていない。だからこそ、悩まなければ良い結果が出ないという感覚の人がいます。そういった思い込みをどう変えていくかが壁だと思っています。
改善のための制度を導入しても、実際に定着させるまでには時間がかかります。私たち経営陣だけでなく、管理職や現場のリーダーが本気で取り組み、対話を重ねながら少しずつ浸透させることで、働きやすい職場へと変わっていくのだと考えています。
「取り組み」を「仕組み」に落とし込むこと
働きやすい職場づくりの中で、大切にされていることは?

村尾社長:取り組みを決めるだけではなかなか変わることはありません。大切なのは、それをどう仕組みに落とし込むかです。
例えば残業時間の見える化については、毎月集計してグラフ化し、部門別に共有して客観視を促しています。他には毎週水曜をノー残業デーに設定し、終業チャイムの音楽も切り替えて意識付けしたりしています。
齋藤さん:部門長会議で決まったことが幹部会議に上がり、幹部会議で言われている大事なことを社長が期首会議などでお話して、段階的に周知していくことも仕組みとなっているかと思います。
村尾社長:本気度を伝えるために、語り口を強めて訴えることもあります。部門だけに言っても改善が進まない場合には、担当の取締役を巻き込み、幹部会議で直接訴えることもあります。長時間労働に陥る人ほど、真面目で使命感・責任感を強く持っています。だからこそ、単に「変われ」と命じるのではなく、自分の課題として受け止め、真剣に取り組んでもらえる仕組みが欠かせないのです。
多様な働き方ができる会社を目指して
今後さらに考えられている取り組みはありますか?

齋藤さん:人に優しい制度や設備の整備を考えています。労働時間の適切な管理や色々なことに柔軟に対応できるような制度。それに社内の設備が古くなってきているので、様々な新しい設備を段階的に導入していこうとしています。
村尾社長:ちょっとしたアイデアですが、スポーツ選手が疲労回復に使う酸素カプセルを会社に置けたら面白いなと考えたことがあります。最近では、オフィスに筋トレルームやカフェスペースを設けるなど、さまざまな取り組みをしている企業もありますよね。
私は、社員が必要とするものであれば何でも取り入れて良いと思っています。ただし、私が一方的に決めてしまうのではなく社員の側から「欲しい」「やってみたい」と提案してもらい、会社として柔軟に応えていける環境をつくりたいです。
基本的には、一人ひとりにライフプランがあり、それに応じた働き方ができる組織が求められているのだと思います。そして、そうした会社にこそ人が集まってくるのでしょう。例えば、できるだけ長く働き続けたい人もいれば、働く期間や頻度を自分で決めたい人もいます。そのどちらにも対応できる制度が、これからますます必要になってくるはずです。
組織づくりも含めて難しい時代だと感じていますが、こういった取り組みをする中で心に残っているお話があります。サイボウズ株式会社の青野さんの講演です。そこで紹介されたのは「僕は週3がいいです」「週2がいいです」「午前中だけ働きたい」といった、多様な働き方をパズルのように組み合わせて実現しているチーム作りでした。
うちの会社ではまだ想像もつかない段階ですが、いつかそうした働き方を実現できるように、これからも取り組みを続けていきたいと思います。
企業情報
株式会社村尾技建
1975年設立。新潟市中央区に本社を構える村尾技建。設立以来、地質調査・建設コンサルタント業を手がける。従業員数は54名。うち17名が女性。(※令和7年9月時点)