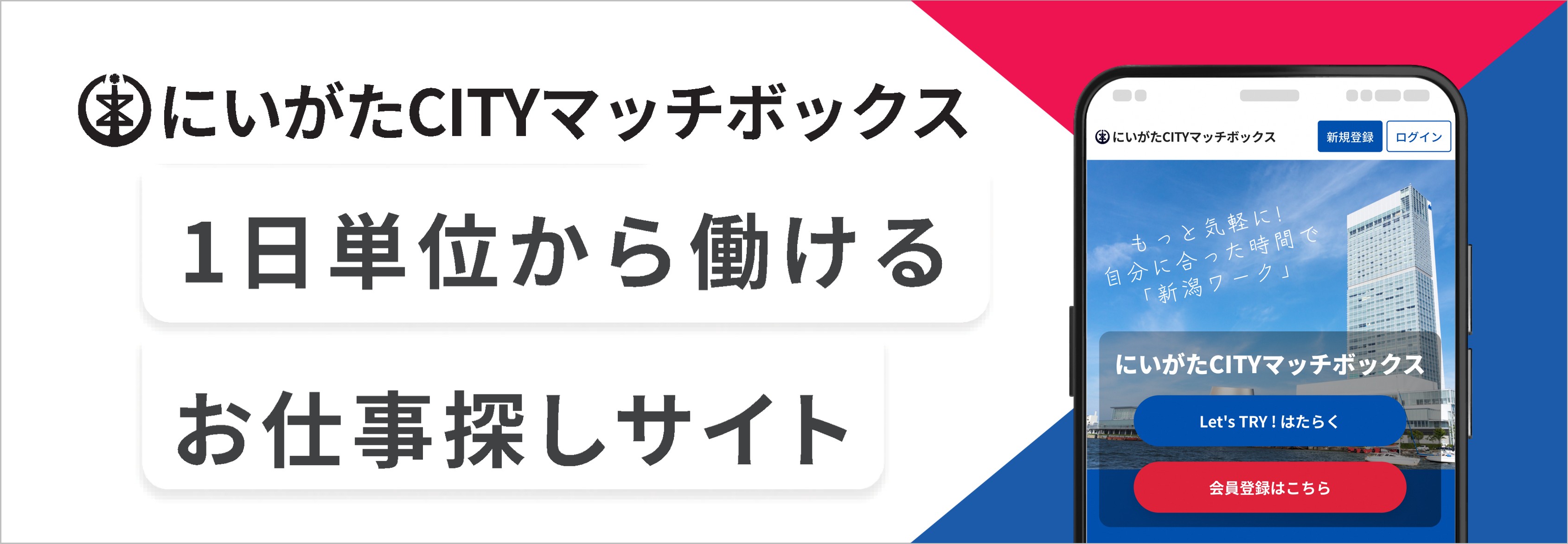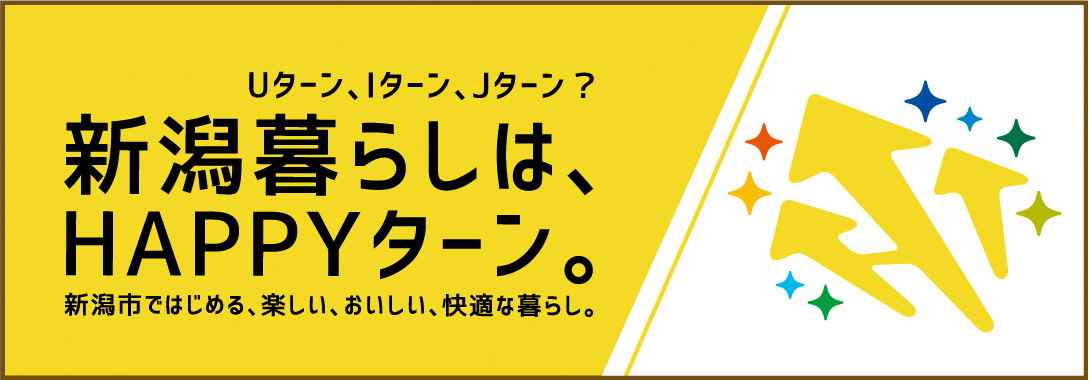interview インタビュー
【令和6年度 働きやすい職場づくり推進企業表彰 優秀賞を受賞】人への投資を中心に従業員の意見に耳を傾け、一体となって目指す魅力的な職場

新潟市東区に本社を構える株式会社中喜。「従業員満足」「従業員が健康的で健やかに働けること」に積極的に取り組み、「令和6年度新潟市働きやすい職場づくり推進賞 優秀賞」「新潟市健康経営優秀賞」にも選出されました。その取り組みの経緯や工夫について、代表取締役社長の中村 太郎(なかむら・たろう)さん(以下、中村社長)、執行役員・総務部 部長 関口 道子(せきぐち・みちこ)さん(以下、関口さん)にお話を伺いました。
いつかくるとわかっていた人手不足を見据えて
働きやすい職場づくりに取り組み始めたきっかけを教えてください。

中村社長:時期としては2018年頃です。右肩上がりではない業界の中小企業で、なかなか採用を始めることができていませんでした。ご存知のように建設業は新しい人がなかなか入ってきづらい業界です。若手と呼ばれていた人が気づけば40代後半から50代…という感覚です。

自社で内装した社内オフィスエリア
ゆくゆくは人手不足になるということがわかっていたので、その時にすぐ募集はできませんでしたが、始めようと思った時に、すぐに魅力ある会社だと認知してもらえるように準備は進めていました。
同じ頃、東京営業所の社員が突然倒れ、引き継ぎができないまま現場が混乱してしまうという出来事がありました。「社員の健康は会社のリスクだ」と痛感し、禁煙や生活習慣の注意を促すだけではなく、健康そのものを経営課題として扱い、制度と運用で守る方向へ舵を切りました。
現在、社内には30代・40代を中心に18~19歳の新卒から50代の管理職、70代のベテランまで幅広い世代がいます。人材の流動性が高まる時代だからこそ、今いる社員に辞められることが一番困ります。新入社員が育つまでには時間がかかるので、新しい人が入りたくなる会社でありながら、今いる社員にとっても働きやすく、長くいてもらえるような職場であることを一つの物差しにして、色々な施策を試みています。
思いつきで終わらせず「仕組み化して回す」
「働きやすい職場」を実現するために、どのような取り組みを行っていますか?

トレーニングルーム
中村社長:思いつきで終わらせず「仕組み化して回す」ことを重視しています。例えば、部長が部下と月一回面談する1on1ミーティングもその一つです。目標シートをもとに進捗や悩みを聞き取り、その内容を部長間で共有。部署横断で支援し、課題の早期解消につなげます。小さな違和感の段階でケアすることが狙いです。

休憩室
また、オフィス環境の改善にも力を入れていて、快適でストレスの少ないオフィス環境づくりに取り組んでいます。
社員との雑談や社内アンケートの声を拾い、コーヒーサーバーの導入、トレーニング器具の整備など、随時改善を重ねています。
関口さん:アンケートはLINE WORKSを使ったアンケートなので回答しやすいと思います。好きな時間に回答できたり、回答を忘れている人にはリマインドできるため便利に活用しています。
中村社長:生産性向上につながるためにデジタルツールの活用でやれることは全部やろうと思って実施しています。
連絡手段はLINE WORKSを導入しています。最初は「同じフロアにいるなら口頭でよいのでは」という声はありましたが、メリットを具体的に共有し、まずは使ってみる体験をしてもらいながら定着させました。
現在AI活用を進めようとしていますが、社内の反応を見ながら進めています。まず、私や担当者で始めてみてから部長に共有し、そこから全社に広めるというやり方でいつも進めています。社内のデータを集積してChatGPTみたいに検索できるようなシステムも作っているんですよ。
新しいことを導入する時にそこまで障壁を感じたことはないですね。やってはみたけどあまり浸透しないということは、たまにあります。ただ、それは単に制度設計がいまひとつでニーズを把握しきれていなかったということだと思いますので、反省して次に活かすようにしています。
「つくる人を次の時代へ」を掲げ、人への投資を会社の中心に
どのような想いで働きやすい職場づくりに取り組まれていますか?
中村社長:働きやすい職場づくりへの施策は、少し前から色々なことを行っていたのですが、「なぜこの施策を会社として行うのか?」という根本的な部分を昨年部長以上で話し合いました。そして、2024年に企業理念「つくる人を次の時代へ」を掲げ、人への投資を会社の中心に据えました。
採用面では2023年から新卒採用を継続して行っています。今年度は20代前後の新入社員が5名程入社しました。当社の規模で新入社員が増えていくことは、育成する側にとって大きな責任の伴う挑戦となります。だからこそ、目的・目標・ミッション・ビジョンを明確にし、全員で共有しています。思いつきではなく今後の当社にとって必要で意義のある取り組みだからこそ、「簡単ではないけれど、これから一緒に会社を担う仲間を育てるために頑張っていこう!」という想いで取り組んでいます。
関口さん:ミーティングの度に、そういった方針の話を社長はしています。継続的に共有することで浸透させようとしていますね。
中村社長:忙しい時期には申し訳ないなと思いながらも、頑張ってもらっています。頑張ることで新入社員が成長してくれれば、明るい未来が待っていると考えています。
「見て覚えろ!」禁止。丁寧な人材育成への試み
人材育成においてはどのような取り組みを行われていますか?
中村社長:「見て覚えろ!」は禁止にして、丁寧な育成に取り組んでいます。高卒採用も行っているのですが、いきなり現場に出されて何もできない新人に対して厳しい言葉が飛ぶのがこれまでの建設業の通例でした。しかし、それでは早期離職につながってしまいますし、成長も遅い。そうならないように倉庫内に実習スペースを設け、新入社員は約3か月間「貼る・ばらす・組む」といった一連の作業を模擬現場で徹底して練習できるような体制を整えました。実習により安全と品質の基礎を固めてから現場へ送り出すことができます。短期的には売上にならない投資ですが、長期的に若手の離職を防ぎながら成長を促すことになると思います。
AI活用などによる効率化は今後も進んでいくと思いますが、現場がAIやロボットで完全に補える未来を私はまだ想像できません。そうなると、人手不足の中で人を育てていかないと物作りができない時代になるという危惧があります。そこをなんとか頑張って若い人を育てられたらと思っています。
9連休を取得した社員に手当を支給する『長期連続休暇奨励制度』
特に力を入れているのはどのような取り組みですか?

中村社長:『長期連続休暇奨励制度』は、2年前に作った制度です。建設業なので、繁忙期に土日も出勤しなければいけなかったり、残業があったりというのはうちの会社だけではなく、業界全体がそうなので致し方ないという状況でした。ただ、閑散期になっても皆休みをなかなか取りませんでした。
それは「お前、有給なんか取るなよ」と言われているわけではなく、「あの人が出勤しているのに、自分だけ休むわけにいかない」という、真面目な思いからそういう状況が生まれてしまうんですよね。一昔前ですと、律儀で褒め称えられていたかも知れませんが、忙しい時期があるから休めるときは休んで欲しいということなんです。
そこで作ったこの制度では、有給・代休・土日祝を組み合わせて9連休を取得した社員に手当を支給。さらに、その間のサポート役を引き受けた社員にも手当を出します。有給を取る際にしわ寄せを食ってしまう人に配慮して休めないのであれば、その人にも手当を出せば、お互いwin-winだから休みやすくなるのではないかと考えました。
この制度を考えたきっかけの一つはコロナ禍でした。濃厚接触者が1週間休まなくてはいけない状況で、「これはまずい」となったのですが、案外そうなると1週間休んでも会社は回ることに気づきました。それで、こういった制度も可能なのではないかと思ったんです。
導入して今では工事部はほぼ全員が取得。全社でも8~9割が活用しています。当初は3年に1回の適用でしたが、運用実績を踏まえて2年に1回使えるように改定しました。
関口さん:私は正直言えば、この制度を会社に作るのはちょっと難しいのではないかと思っていました。9連休取ること自体が難しいと思っていたのですが、話を進めて制度の中身が固まっていく中で、「この制度であれば活用したいな」「活用して欲しいな」と思えるようになりました。
中村社長:今では、お盆やGWの前には「今回は誰か使うの?」という話や、「●●さんに休んでもらおうか」と話している部長もいます。そういう声が周りから出るくらい定着してきました。また、健康面では、脳ドック(MRI等)とCTを隔年・会社負担で実施しています。当初は部長職以上を対象にしていましたが、今年の4月から対象社員を拡大しています。実際に早期発見につながった事例もあり、制度の意義を社員と共有できました。
寄り添ったケアで長く働くことのできる環境に
取り組みを通して、どのような変化や効果を感じていますか?
中村社長:厳しい採用環境のなかでも採用がうまくいっている実感はあります。高卒採用は併願不可という事情もあり、入社後のケアに一層力を入れています。新卒の若者も元々いる従業員もほとんど辞めることなく離職率は低い水準で推移しています。今年10年以上勤続の社員が家庭の事情で退職しましたが、例外的なケースです。基本的には長く働き続けられる環境づくりが機能していると感じています。とはいえ楽な仕事ではなく、夏は暑く冬は寒い…そんな中で皆よく頑張ってくれています。
関口さん:社長は社員の率直な意見を全部受け止めた上で、整理して新しい方向を示したり解決方法を考えてくれます。そういった建設的な考え方で仕組みを作っているからこそ、長く働くことのできる環境が作られているのだと感じています。
毎年行う快適なオフィス環境の継続的な改善
今後さらに考えていること、挑戦してみたいことがあれば教えてください。

中村社長:私たちは内装工事の会社なので、快適なオフィス環境の継続的な改善という面では常に続けていきたいと思っています。ディズニーランドの新エリア開業のように、毎年休憩スペース、打ち合わせスペースなど改善されたスペースが増えています。

今年これをやって、来年はこういう風にしようかといったことを、皆で話し合いながら実施しています。今年は、新入社員の施工管理と新入社員の職人チームが、先輩から指導を受けながら一緒に新しい部屋を作りました。時間はかかりましたが、新人の実践トレーニングとしても効果的だったと思います。
従業員と一体となり作っていく「働きやすい職場」
「働きやすい職場」とは、どのような職場だと考えられていますか?

中村社長:安心して快適に働ける環境が整っている職場であり、社員が長く在籍できる職場であると考えています。新入社員が入ってきて、今いる社員が辞めないという現状は、一つの良い物差しになるのかなと思っています。ただ、現状まだまだ道半ばで、大変な部分もあります。社員の皆には申し訳ないなという部分もたくさんあるんですよ。
だからこそ、毎年毎年改善しなくてはいけないことがいっぱいあります。これからも従業員の意見を聴きながら、一体となって「働きやすい職場」を目指していきたいと思います。
企業情報
株式会社中喜
1890年設立。新潟市東区に本社を構える中喜。設立以来、内装事業・建築工事業を手がける。従業員数は27名。うち4名が女性。(※令和7年6月時点)