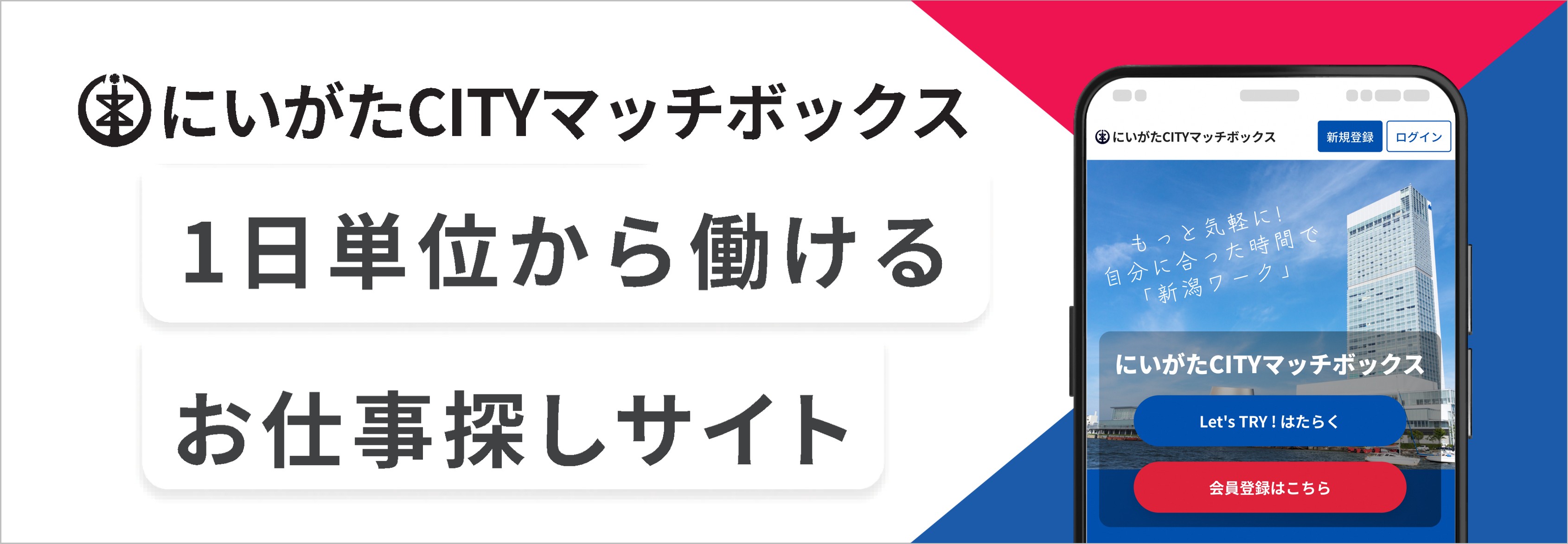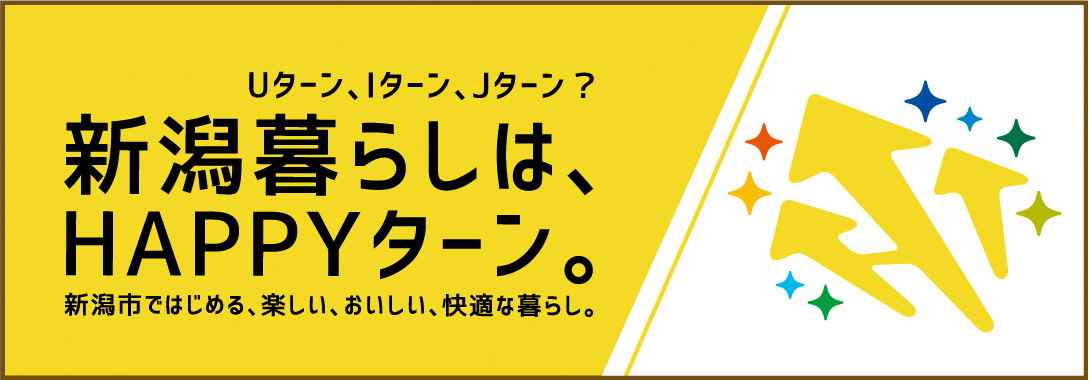Columns & Reports コラム・レポート
イベントレポート
「若手社員を育成する力向上」実践ワークショップ【前編】

新潟市では、市内企業の学び合いや事例の共有、交流を目的とした「企業間ネットワーク」の構築に取り組んでいます。そうしたネットワークづくりの第一歩として、今回は「若手社員を育成する力向上」実践ワークショップを開催しました。
このレポートでは、2025年2月14日に行われた1日目の様子をお届けします。
概要
「若手世代との世代間ギャップがあり、どのように接したらいいかわからない」
「これまでの指導方法では、最近の若手社員が一人前に育たない。定着しない」
「現場では余裕がなく、丁寧な指導ができない」
上記のような「若手社員の育成に関する悩み」を解消し「若手社員が仕事への責任感を持ち、主体的に取り組むようになること」を目指して、以下のカリキュラムでワークショップを行いました。

共通の課題を持つ、学び合う仲間を知る
1日目の会場は新潟市中央区、新潟駅に直結するCoCoLo新潟南館内にある「Sea Point NIIGATA × MOYORe:」イベントホール。親しみやすい雰囲気のフロアで、和やかなムードで開催することができました。
ワークショップ講師はグローリンク株式会社の代表取締役である中藤美智子氏。中藤氏は新卒採用や新入社員研修、中途採用、大学生の就労支援、キャリアデザイン講義など、若い世代の採用・育成に従事した後にグローリンク株式会社を設立。現在は企業の採用コンサルティングを多数手がけられています。

講師の自己紹介が終わった後、参加者も自己紹介を行いました。お話しいただいた内容から、一部抜粋してご紹介します。
「職場で新人と他の職員に年齢差があり、若手への接し方・育成に悩んでいます」
「毎年定年退職者が出るため、新卒採用・育成に力を入れており、知識を増やしたいと思いました」
「新たに採用に関わることになったものの、若い人と接する機会が少なかったため、この機会に勉強したいと思いました」
業種や立場は異なるものの、みなさんが若手社員の育成に課題を感じていることがわかりました。

自己紹介の後には名刺交換も行い、より交流しやすい雰囲気に。共通の課題を持つ仲間として知り合うことができました。

若手世代の価値観・特性を理解する
はじめに「若手社員に対して感じていること、困っていること」というテーマで参加者に意見交換してもらいました。以下に一部をご紹介します。
「若手社員が雑談に加わらないため、人となりを理解するのに時間がかかっています」
「わからないことを聞きに来てくれない、自分から動いてくれないと感じています」
「若い人の中には自分の意見を言えない人がいます」

話し合いの後、講師から「若手世代の特徴」「若手世代が理想とする働き方」「企業を選ぶ際のポイント」「社会における環境・意識の変化」「Z世代を活かす育成方法」についてお話しいただきました。

若手社員との関わり方の基本
続いて若手社員との関わり方の基本として「心理的安全性」や「若手世代とのコミュニケーションを取る上でのポイント」「話やすい場づくりのコツ」「聴き方のポイント」を学んでいきました。

参加者からは「一見『当たり前』と思うことでも『若手社員ができていること』を褒めていくのが大切ではないか」という意見も。レクチャーを受けて、育成者側から若手世代に歩み寄る姿勢の大切さを感じたようでした。
ワークでは「取引先とうまくいっていない若手社員から話を聴くケース」を想定し「聴き方OKパターン」を考えていきました。まず講師から実際にあった「聴き方NGパターン」を聞き、参加者一人ひとりが対応を検討。その後全員で意見交換を行いました。

参加者からは以下のような意見が出てきました。
「まずは『若手社員の言いたいこと』を全部聴いて『そうだったんだね』と受け止めます」
「日々接客を行っている中では、お客様にどのような内容を伝えたか、どのような言葉を使ったかを聴き、今後どうしたらいいかを考えてもらっています」
「営業職時代の経験を振り返ると、具体的に何があってどのように感じたか、を聴くと思います」

講師からは「若手社員の話を受け止める、事実を教えてもらう、取引先の立場に立って考えてもらう、さらに必要に応じてヒントを出していくことが大切です」とフィードバックがありました。
加えて「話を聴くには時間が必要で、忙しい現場で毎回じっくり聴くのは難しいことも。『やってみた後でうまくいかない場合にじっくり聴く』という形でも良いかもしれません」と具体的なアドバイスも。それぞれの現場で考えるためのヒントをいただきました。
10分間の休憩をはさんだ後、2人1組での「傾聴ワーク」を実施。事前に学んだ内容を取り入れつつ相手の話を聴き合い、フィードバックをもらいました。自分の聴き方について考えながら実践する良い機会となったようです。

「傾聴ワーク」の後は若手社員への対応実践編として、議事録作成に関するケーススタディを実施。現場で実際にありそうな若手社員の発言に対して、指示どおりに動いてもらうにはどのように伝えると良いかを考えていきました。

参加者からは以下のような意見が出てきました。
「議事録を何のために作るか、目的を伝えないと理解が得られないのでは」
「自分が議事録作成を経験していたとき、目的を確認して作成方法を見直していきました」
講師からは、傾聴、価値観の尊重、目的・具体性の伝達に加えて、伝わったか確認すること、フィードバックの大切さなどを教えていただきました。
最後に、講師から「若手社員を育成する際のポイント」「成長を支援するマネジメント」「若手世代のキャリアに関する価値観」などを伺って1日目が終了。3時間のカリキュラムでしたが、あっという間に感じられました。
ワークショップの終わりに、参加者からは以下のような感想が寄せられました。
「コミュニケーションツールなども活用しながら若手社員に情報共有をすることで、もっと仕事について理解してもらう工夫ができればと思いました」
「講義や他社事例をお聞きし、ディスカッションする中で頭が整理されました」
1日目のワークショップで自社と他社を比較しながら、若手世代の理解が深まり、コミュニケーションの取り方についてヒントが得られたようです。
ワークショップ2日目についてもレポートしています。ぜひご覧ください。
新潟市では今後も働き方改革やウェルビーイングをテーマとしたセミナーの開催や、企業間のネットワークづくりに取り組んでいきます。ぜひ、働きやすい職場づくりにお役立てください。ご参加をお待ちしております。