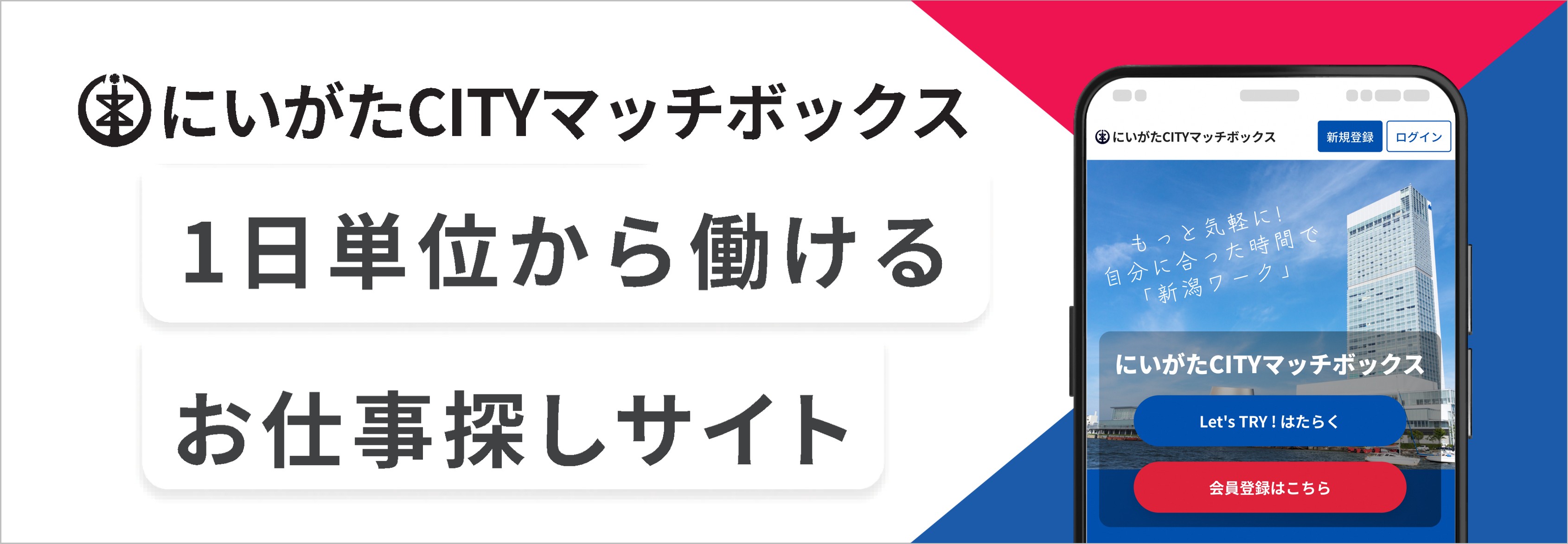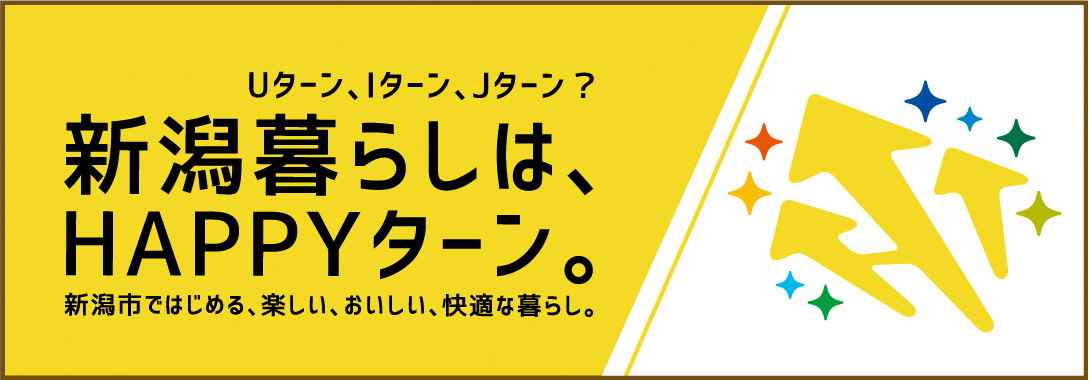Columns & Reports コラム・レポート
AIで変わる働き方
生成AI活用事例 〜ビジネス開発編〜
地域企業にとって「自社の強みを活かした新規事業の立ち上げ」は、常に頭を悩ませる大きな課題です。近年、この課題解決の新たなアプローチとして注目を集めているのが「生成AI」の活用です。
本コラム第3回では、生成AIを活用したビジネス開発の具体的な導入例とともに、そのポイントを解説します。
執筆者プロフィール
山田 崇
株式会社ドコモgacco
Chief Learning Officer/地域越境ビジネス実践プログラム責任者
大学卒業後、長野県 塩尻市役所入庁。地方創生や官民連携事業に従事。地域課題の解決と企業の人材育成を組み合わせた越境プログラム「MICHIKARA(ミチカラ) 地方創生協働リーダーシッププログラム」を立ち上げる。地方創生の取り組みをまとめた書籍『日本一おかしな公務員』を日本経済新聞社から上梓。2022年、24年間勤務した塩尻市役所を退職し、NTTドコモに転職。現在はドコモgaccoで「地域越境ビジネス実践プログラム」の責任者を務める。また、信州大学 キャリア教育・サポートセンター 特任教授(教育・産学官地域連携 分野)として「地域活性化システム論」、地域企業との共同研究による「アントレプレナー実践ゼミ」、全学横断特別教育プログラム「ローカルイノベーター養成コース」を担当。2016年から内閣府 地域活性化伝道師。

AIがもたらすビジネス開発の変革
生成AIが近年大きく注目されている理由は、単なる業務効率化だけでなく、新たな価値創造やビジネスモデルの刷新をも可能にする点にあります。たとえば、大量のデータを分析し、そこから得たインサイトを基に新商品コンセプトを提案したり、地域特有の強みを生かした新ビジネスを生み出したりすることが期待できます。
マーケティングの分野でも、AIがユーザーの検索キーワードやSNS投稿を解析することで、トレンドの兆しや潜在顧客層をより早期に発見できるようになりました。
その結果、これまでアプローチしきれなかったターゲットとの新たな接点が生まれます。また、AIによる自動広告運用の精度が高まっているため、広告費を最適に抑えつつ、狙った顧客層へ効果的にリーチできるようにもなっています。

具体的な事例紹介:新潟日報生成AI研究所の取り組み
研究所設立の背景
新潟日報社は、2024年11月1日の創刊記念日に合わせて「新潟日報生成AI研究所」を子会社として立ち上げました。もともと同社では、2024年4月に社長直轄の「デジタル戦略特別室」を設置し、社内DXや外部連携による新サービス開発を推進していました。その流れの中で、急速に注目を集める生成AIを地域企業にも普及させ、新潟の産業活性化に貢献する“旗振り役”として研究所の設立に至ったそうです。
新聞社が本格的に生成AIを活用し、BtoB向けのサービスを提供する取り組みは全国的にも珍しく、地域における新規ビジネス開発やAI普及のリーディングケースとして注目を集めています。
新聞社ならではのデータ活用
同社が長年蓄積してきた新聞記事データ(2010年以降)を、株式会社エクサウィザーズの「ExaBase 生成AI」をベースとしたプラットフォームに連携。事故・事件・お悔やみなどのセンシティブな個人情報を除いたうえで、約15年分の膨大な地域情報を生成AIで横断検索・要約できるようにしました。

従来の過去記事データベースやニュースサイトとの大きな違いは、「ユーザーが必要とする観点で情報を加工し、短時間で取得できる」点です。たとえば、地元企業の営業担当者が訪問先企業の動向や関連トピックをAIに尋ねれば、新聞記事をもとに確度の高い情報がすぐに得られます。
地域の情報資源を最大化
地域の情報は、インターネット上に十分な量があるとは言えず、通常の生成AIでは誤った情報(ハルシネーション)を提供してしまうリスクがあります。しかし、新潟日報生成AI研究所が提供する生成AIツールでは、長年の取材で蓄積してきた信頼性の高い地域情報を活用できるため、正確で実践的なデータが得られます。
また、もともと電子化された記事データやデータベースサービスを提供してきた経緯があるため、生成AIに連携するデータを迅速に整備できたことも強みとなっています。
地域企業の新たなビジネス創造を後押し
すでに十数社が同ツールを利用し、新規ビジネスの検討にも活用が始まっているといいます。たとえば、生活面と経済面の記事を読み比べ、生活者のトレンドを把握すると同時にビジネス面での動向を探るという使い方です。従来であれば図書館などで実際の紙面を見比べる必要があった作業を、生成AIがサポートすることで効率的にアイデア創出が可能になります。

現在は県内企業の利用が中心ですが、新潟に進出したい県外企業にとっても、地域特性を深く理解しながら自社の強みを組み合わせるうえで有用なツールとなっています。
新技術と地域の架け橋へ
今後、新潟日報生成AI研究所では、新聞記事をもとにした生成AIツールだけでなく、新たなAIツールの提供も計画しています。たとえば、地域のサッカークラブなどのIP(知的財産)と協働したAIアバターとの対話練習サービスを試験提供しており、さらなる可能性を探っています。
新聞社ならではの地域ネットワークや情報資源とAI技術を融合させることで、自治体や企業のDXを後押しし、人口減少や若年層の流出によって地域企業が抱える人材確保等の課題解決、さらには産業力の底上げと地域全体の活性化を目指しています。

導入・運用のポイント
1. データの活用と顧客理解
AIはデータが豊富であるほどその真価を発揮します。自社が保有する顧客データやSNS投稿、ECサイトでの購買データ、アンケートなどをまず棚卸ししましょう。
ただし、AIが導き出す分析結果を鵜呑みにするのではなく、実際の顧客との対話や現場感覚を組み合わせることで、より精度の高い戦略を構築できます。
2. 社内外の協力体制
AIの活用を成功させるには、マーケティング部門だけでなく、販売や開発部門などの連携が欠かせません。AIが提案するアイデアをどのように実装するかについて、社内全体で検討する必要があります。
また、外部のAI専門家やコンサル企業に協力を仰ぐことで、技術的課題やデータ分析ノウハウを補い、短期間で成果を出しやすくなります。

まとめ・今後の広がり
生成AIは、地域企業にとって「ビジネス開発を変革する強力な手段」です。新潟日報が設立した生成AI研究所のように、企業や地域特性、AI技術を組み合わせることで、新たな価値やイノベーションを生み出すことが可能になります。地域独自のブランド力や特産品の魅力を世界へ向けて発信するうえでも、AIによるデータ分析やマーケティング支援は今後ますます重要になるでしょう。
多様な資源を活用できる地域企業こそ、「AI+現場力」の相乗効果で大きく飛躍できる可能性を秘めています。ぜひ、生成AIを活用して、新たなビジネスチャンスを掴んでいただければと思います。